2021年12月13日
家族信託の受託者を法人にするとは?
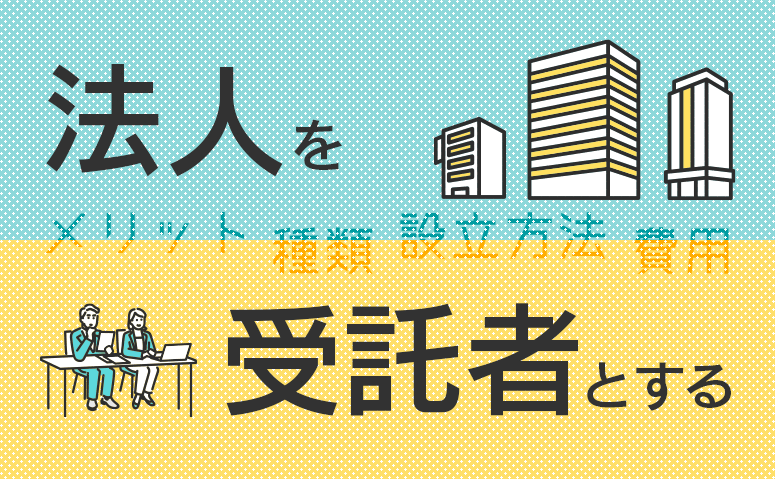
信託財産の管理・処分(運用や売却など)を行う受託者は家族信託のキーパーソンといえます。「パーソン」といっても受託者は個人のみではなく法人でも就任することが可能です。本コラムでは法人を受託者にするメリットや適任である法人の種類、法人の設立の方法から、かかる費用までを解説します。
家族信託における法人が受託者になるとは<商事信託と民事信託>
法人が受託者になると聞いて、信託会社や信託銀行が思い浮かんだ方もいると思います。
これらの法人が営利目的で報酬(信託報酬)を受け取り、行う信託は「商事信託」と一般的に定義されます。商事信託は信託法と信託業法の規制を受け、信託会社も内閣総理大臣の免許(運用型信託会社)または登録(管理型信託会社)が必要です。
これに対して、家族信託のような営利目的ではない信託は、商事信託に対して一般的な定義として「民事信託」と呼ばれます。信託報酬を目的としない民事信託では、受託者である家族などが信託業法の規制を受けずに信託行為を行うことができます。家族信託は信託会社や信託銀行が行う信託とは一線を画すものです。
家族信託における法人が受託者になるというのは、家族や親族によって設立された法人が受託者に就任することを想定しています。つまり、法人になったとしても信託財産の管理・処分の実質的権限は家族や親族にあるということです。
受託者を法人にするメリット
ではなぜ、わざわざ法人を受託者にする必要があるのでしょうか。まずは法人を受託者にするメリットについて説明します。受託者を法人にすることには
- 家族信託の予期せぬ終了を防止する
- 受託者の変更手続きを簡略化できる
といったメリットがあります。
家族信託の予期せぬ終了を防止する
家族信託には信託法によって定められた終了事由があります。その中でも特に注意すべきなのが、家族信託の当事者の意思とは関係なく、家族信託が終了してしまう事由になります。それが
- ① 受託者が不在の状態が一年間継続したとき
- ② 受託者と受益者が同一である状態が一年間継続したときです。
どちらも受託者に関わりのある終了事由となっています。
①の「受託者が不在の状態が一年間継続したとき」は受託者が死亡や病気、怪我などによりその任務ができなくなった場合に発生するおそれがあります。予備的な受託者を選任しておく、次の受託者の選任方法を規定しておくなどの対策も考えられますが、受託者が法人であれば、そもそも死亡や病気、怪我という事態が発生することがなくなります。
②の「受託者と受益者が同一である状態が一年間継続したとき」は受益者連続信託(受益者が死亡した際に、新しい受益者となるものが定められている信託)の場合に特に注意すべき事由です。
例えば『委託者:親 受託者:子 受益者:親→子→孫』のように委託者である親の資産を、受託者である子に信託し、当初の受益者を親とします。その後、受益権を親が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫へと承継させていこうとする家族信託を行ったとします。この家族信託において、親の死亡後に受益権が子へ承継されると、子は受託者と受益者を兼ねることになります。そして、この状態が1年間継続すると家族信託は強制的に終了となり、孫に受益権を承継することはできなくなります。
受託者が法人であれば『受託者:法人 受益者:親→子→孫』となり、受託者と受益者が同一になることはありません。
受託者の変更手続きを簡略化できる
家族信託では信託財産は受託者への名義変更が行われます(あくまでも形式的な変更です)。
そのため、受託者が変更されると信託財産の名義を旧受託者から新受託者へ変更する必要が生じます。
例えば、不動産なら受託者変更に伴う所有権移転登記を行う必要があります。現金は、受託者名義の信託口口座又は信託専用口座で管理されているのが一般的なので、新受託者が選任されたら変更手続きが必要となります。この他にも火災保険・地震保険の名義変更なども必要です。このような手続きが受託者の変更が生じるたびに行う必要があるのです。
受託者が法人の場合、これらの手続きの手間を軽減できます。
もちろん、法人内で信託財産の管理・処分を行っていた役員が死亡や病気や怪我などにより任務を行うことができなくなるということは起こりえます。その際に、新たな役員が信託財産の管理・処分を行うといったこともあるでしょう。しかし、それはあくまでも法人内の変更であって、受託者が当該法人であることには変わりありません。従って、不動産や預貯金口座の名義変更を行う必要はないのです。
法人の種類
法人には「株式会社」や「有限会社」「一般社団法人」「一般財団法人」などの種類があります。では、家族信託の受託者とする場合にはどの種類の法人が適任なのでしょうか。皆さんにとって馴染みがある法人は株式会社であると思いますが、実務上では「一般社団法人」が適任であると考えられます(詳細は後述します)。
一般社団法人とは
一般社団法人は「非営利法人」です。非営利と聞くと「利益を出してはいけない」とお考えの方もいると思います。しかし、ここでいう「営利」は「収益事業を行い、利益を上げる」という意味ではなく、「余剰利益を分配する」という意味です。例えば、営利法人である株式会社は株主に配当金を渡すことができますが、一般社団法人はそのようなことはできません。しかし、利益を上げることを禁止されているわけではありません。
一般社団法人は収益事業を行い、利益を上げることができますし、逆に利益を上げないことも可能です。
一般社団法人の機関構成
一般社団法人は主に社員と理事で構成されています。社員とは会社でいう従業員ではなく、会社でいう株主の立場です。社員は社員総会を構成します。社員総会は一般社団法人の意思決定機関であり、一般社団法人に関する事項を決議します。次に理事ですが、理事は社員総会で選任されることにより就任します。社員総会が意思決定をする機関であるのに対して理事は社員総会の決定に基づいて業務を遂行します。家族信託における手続きで例えると、信託財産である不動産を売買する場合には、社員総会にて売却の決定を行い、理事が売却の手続きを行うことになります。
家族信託の受託者に適任である理由
前述の通り、一般社団法人では収益事業を行い、利益を上げるかどうかは自由となっています。それに対して、会社は営利法人であり、利益を上げる活動を行うことが前提とされています。「家族の老後の安定した暮らしのサポート」や「円滑円満な資産承継の実現」を目的に家族信託に取り組むことがありますが、これらの目的には利益を上げるという性質はあまりありません。従って、利益を上げないことを目的とする活動も問題なく行うことができる一般社団法人の方が家族信託の受託者として適任であるといえるでしょう。(株式会社は家族信託の受託者になることができないというわけではありません)。
一般社団法人の設立方法
次は一般社団法人の設立方法について見ていきましょう。一般社団法人は最低2名の社員と1名の理事が必要です。ただ、社員と理事は兼任が可能なので、延べ2名で設立が可能となります。社員数が多い大規模法人では、迅速な意思決定のために理事会を置くこともありますが、家族信託の受託者とする一般社団法人ではそこまで考える必要はないと思います。まず、2名以上の設立時社員(設立後の社員になる者)が設立の発起を行います。なお、設立の手続きは、もちろん自分で行うこともできますが、高度な法的知識が必要となります。その後の信託契約締結のことも考えると、司法書士や行政書士をはじめとした法律専門家に手続きを依頼することがほとんどかと思います。
定款案の作成・認証
まず、設立時社員は定款を作成します。一般社団法人の定款には
- 一 目的
- 二 名称
- 三 主たる事務所の所在地
- 四 設立時社員の氏名または名称及び住所
- 五 社員の資格の得喪に関する規定
- 六 広告方法
- 七 事業年度
を記載する必要があります(一般社団・財団法人法第11条1項)。
この中でも特に注意すべきは「目的」になります。法人が行う「営利を目的とする不特定多数を対象とする」信託は商事信託とされ、信託業法の適用を受けてしまいます。そこで目的の記載によって当該一般社団法人が営利目的ではない信託のために設立されたものであることを明白にする必要があるのです。具体的には以下のような目的を記載します。
当法人は、○○家の幸福な生活と福祉を確保し、もって生涯にわたる○○家の安定した生活と最善の福祉を確保するための支援を行うことを目的とし、以下の事業を行う。
- 1. 信託業法の規制を受けない民事信託の受託
- 2. 前号に付帯する一切の業務
定款を作成したら定款認証を受けます。定款認証とは当該定款(原始定款といいます)が正当な手続きによって作成されたものであることを公証人に証明してもらうことです。
設立登記を申請する際には認証を受けた定款が必要となります。なお、定款認証を受ける際には公証役場に手数料を支払う必要があります(詳細は後述します)。
理事の選任
設立時社員は理事や代表理事を選任します。理事・代表理事は定款に記載して定めることもできますし、定款作成後に設立時社員が選任することも可能です。
設立登記
定款を作成し、書類の準備が整ったら、設立登記を申請します。登記は当該一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する法務局に行います。登記を法律専門家に依頼する場合は司法書士に依頼することが一般的です。また、信託契約が締結されると信託財産たる不動産は委託者から受託者である一般社団法人への所有権移転登記が行われますが、それも司法書士に依頼することが一般的です。
一般社団法人にかかる費用
最後に一般社団法人にかかる費用について、設立時にかかるものと設立後にかかるものにわけて見ていきます。
設立時
一般社団法人を設立する際には定款認証の手数料と設立登記の登録免許税がかかります。定款認証の手数料は5万円、設立登記の登録免許税は6万円です。また、この他にも法律専門家に設立の手続きを依頼した場合には別途専門家への報酬が必要となります。
設立後
一般社団法人には法人税や法人事業税、法人住民税が課せられます。このうち、法人税及び法人事業税は法人の所得に対して課税されます。そのため、当該法人に利益がない場合はこれらの税金はかかりません。法人住民税に関しては、法人税割と均等割があり、法人税割については所得が無ければ課税されません。それに対して均等割りは所得がなくても課税され、その額は年額7万円です。一般社団法人は最低でも毎年7万円の法人住民税がかかります。
また、理事が変更する際には変更登記を行う必要があります。一般社団法人の理事には2年の任期があります。たとえ、理事本人に辞める意思がなくても任期がくれば退任します。退任した者が理事を続ける場合は定時社員総会にて選任する必要があり(重任といいます)、その旨を登記する必要があります。つまり、最低でも2年に1回は社員変更登記を行う必要があり、1万円の登録免許税がかかります。なお、社員は登記事項ではないので社員が変更しても登記を行う必要はありません。
また、この他にも税務申告や法人登記の手続きを依頼した場合には、税理士や司法書士などの専門家への報酬が別途必要となります。
まとめ
以上が法人を受託者にすることについての説明です。確かに法人は、受託者が個人の場合にはかからない費用が発生します。また、設立の手続きや設立後においても定期的に総会を開き、総会議事録を作成しなければならないといった手間もかかります。しかし、受託者を法人にすることにより、受託者不在のリスクを防ぎ、受託者交代の手続きの手間を減らすといったメリットを得ることができます。
家族信託は一度開始すると、場合によっては何十年も続くものです。
例えば、『委託者:親(70代)受託者:子(50代)』という家族信託を始めたとします。高齢により判断能力が心配になってきた親に代わって、働き盛りの子が信託財産の管理・処分を担うといった構造です。しかし、20年後は『委託者:親(90代)受託者:子(70代)』となります。近年、65歳以上の高齢者が65歳以上の高齢者を介護する「老々介護」が問題となっていますが、将来的には「老々信託」といった事態も発生する可能性もあります。家族信託は10年後、20年後に起こるリスクも考慮して、取り組む必要があるのです。その対策の1つとして受託者を法人とすることは検討に値するといえるのではないでしょうか。

