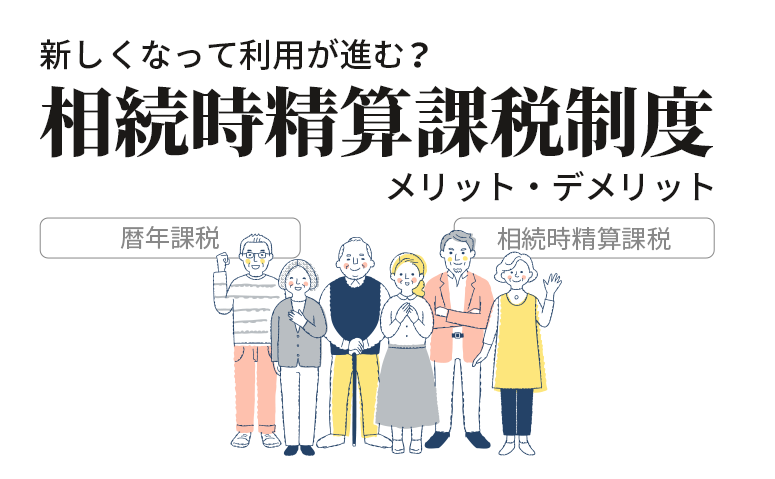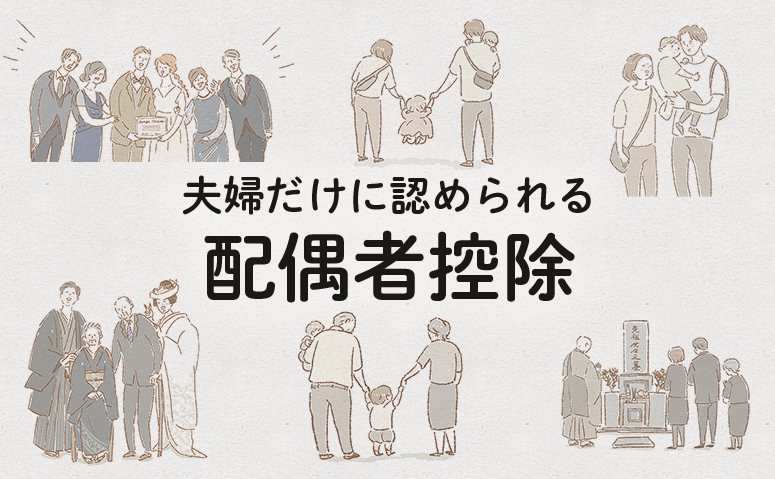家族信託が注目される背景
出生率や婚姻率の減少などによる少子化と高寿命化の進行により、我が国では、人口減少・高齢化社会の到来を迎えています。(図1参照)ここでは、家族信託が必要とされる背景にある「高寿命化」にスポットを当てて、考えてみましょう。
- 図1 年齢区分別将来人口推計と高齢化率
出典:内閣府「令和2年版高齢社会白書」高齢化の推移と将来推計より当社加工
長生きすることは喜ばしいことであり、元気に(健康に)寿命を全うできれば、それに越したことはありません。しかし、実際には平均寿命と健康寿命(日常生活に制限のない期間の平均値)の間にギャップがあり、このギャップに高齢化社会の問題点が潜んでいます。
(図2参照)
- 図2 平均寿命と健康寿命
出典:内閣府「令和元年版高齢社会白書」健康寿命と平均寿命の推移
健康でない状態(病気や介護が必要な状態)になった場合のリスクとして挙げられるのは、介護費用や生活費など、金銭面の問題はさることながら、近年、認知症患者数の増大により、「自分の意志で物事を決めることができなくなるリスク」が注目されています。厚生労働省発表のデータによると、2030年には65歳以上の高齢者のうち、およそ3人に1人は認知症か、その前段階の「軽度認知障害(MCI)」になると見込まれており(図3参照)、もはや、誰もが認知症になるリスクを抱えている時代であるといえるでしょう。
- 図3 65歳以上の認知症患者数とMCI(軽度認知障害)患者数の将来推計
出典:「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」
《令和5年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)》九州大学二宮利治教授より当社作成
では、不動産オーナーが認知症になってしまった場合、どのような問題が起こり得るのでしょうか?
判断能力の低下した高齢者をめぐる犯罪やトラブルの増加といった社会背景の中、令和2年4月1日に施行された改正民法において、意思能力に関する条文が明文化されました。
- 意思能力(改正民法 第3条の2)
- 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
不動産オーナーが認知症により意思能力の無い状態となってしまった場合、施設入居後の自宅の売却、アパート・駐車場の賃貸借契約の締結、アパートの大規模修繕工事・建て替え・預かり敷金の返却/受入れといった契約行為が無効となることが明文化されたことになります。当然のことながら、家族が代わりに契約行為を行うことはできません。
また、口座名義人の判断能力が著しく低下したことを銀行が知った場合、その時点から銀行口座は凍結されてしまいます。
戸籍抄本などで家族関係が証明され、施設や医療機関の請求書で使途が確認できれば、認知症患者の家族が口座からお金を引き出せるよう、全国銀行協会が業界統一の対応を促す通達を2020年3月に出しましたが、あくまで入院費用等に限られます。
つまり、適切なタイミングで預貯金を引き出したり、不動産を売却したり、修繕したりすることが一切できなくなり、不動産の管理・処分・活用、すべてにおいて、大きな弊害・機会損失が生じ、家族にも負担をかけることになってしまいます。
このように、高齢者が自らの意思で自らの財産(不動産や預貯金など)を安全に管理し続けることが難しくなってきている現状の中、高齢者の新しい財産管理手法の必要性が叫ばれ、「家族信託」が注目され始めているのです。