2021年5月13日
遺留分ってなに?『遺留分侵害額請求』とは
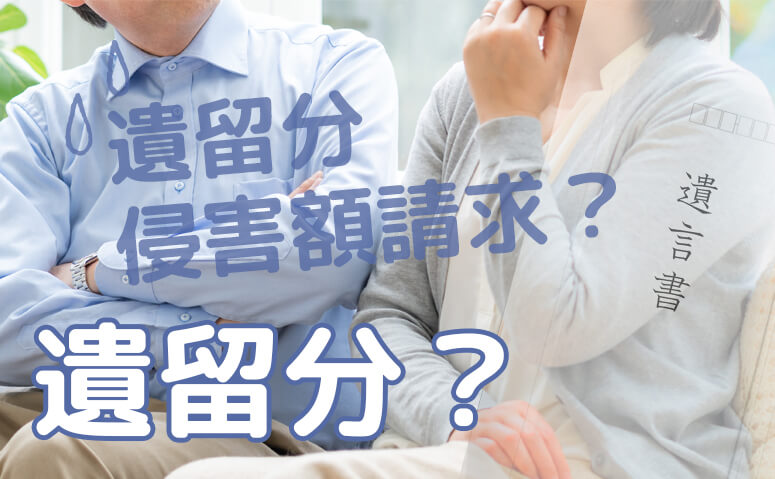
相続の際、「遺留分」が問題になることがあります。「遺留分」は相続人に法律上確保されている財産の取り分です。遺言書では原則として自由に財産を処分できますが、相続人の遺留分を奪うことはできません。
本記事では、「遺留分」とは何かについて、わかりやすく説明します。相続の場面で「遺留分」を奪ったり奪われてしまったりした場合にはどう解決すればよいのかも知っておきましょう。
1.遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合を言います。遺留分については、民法に具体的な割合が定められています。
(1)民法上相続人になる人
まず人が亡くなったとき、誰が民法上の相続人(法定相続人)になるかを確認しておきましょう。
法定相続人になるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者、子供、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の人の優先順位は次のようになっており、先順位の人がいない場合にのみ相続人になります。
| 第1順位 | 子供(亡くなっている場合には孫など) |
|---|---|
| 第2順位 | 直系尊属 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥・姪) |
つまり、相続人の組み合わせとしては、
- 1)配偶者のみ
- 2)配偶者と子供
- 3)配偶者と直系尊属
- 4)配偶者と兄弟姉妹
- 5)子供のみ
- 6)直系尊属のみ
- 7)兄弟姉妹のみ
という7つのパターンがあります。
(2)相続分と遺留分
民法では法定相続人が相続できる財産の割合(法定相続分)が定められています。また、法定相続分とは別に、最低限の取り分として、遺留分の割合も定められています。
法定相続分及び遺留分は、相続人の組み合わせ(上記1)~2))によって変わります。ただし、兄弟姉妹には遺留分はなく、次のようになります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 1)配偶者のみ | 配偶者が全部 | 配偶者1/2 |
| 2)配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2 | 配偶者1/4、子供1/4 |
| 3)配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |
| 4)配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 配偶者1/2、兄弟姉妹はなし |
| 5)子供のみ | 子供が全部 | 子供1/2 |
| 6)直系尊属のみ | 直系尊属が全部 | 直系尊属1/3 |
| 7)兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹が全部 | 遺留分のある人なし |
(3)遺言書がない場合
遺言書がない相続では、「法定相続人が法定相続分を相続する」というルールが適用されます。法定相続人は遺留分よりも多い法定相続分を相続できるので、遺留分を持ち出す必要はありません。
(4)遺言書がある場合
遺留分が関係してくるのは、被相続人が遺言書を残している相続です。遺言書があれば「法定相続人や法定相続分を相続する」というルールは適用されず、遺言書に従って財産を分けるのが原則となります。しかし、遺言書に100%従うとなると、不都合が生じることがあります。
たとえば、被相続人の財産が家のみであるにもかかわらず、遺言書に見ず知らずの第三者に家を譲ることが書かれていれば、被相続人の配偶者や子供などは困ってしまうでしょう。こうした不都合を防止するため、被相続人に近い親族については、遺留分としてある程度の財産が確保されています。
(5)遺留分の例合
たとえば、被相続人の残した財産が現金4,000万円で、相続人が妻と息子1人である場合(上記2)のパターン)、妻と子の遺留分はそれぞれ4分の1です。被相続人が全財産を友人に譲る旨の遺言書を書いていたとしても、妻と息子はそれぞれ1,000万円を相続することができます。
2.遺留分侵害額請求とは
遺言書の内容にかかわらず、遺留分については確保できることを説明しました。ただし、実際に遺留分を相続するためには、「遺留分侵害額請求」という手続きが必要になります。以下、遺留分侵害額請求とはどんな手続きかを説明します。
(1)遺留分を相続する意思表示
遺言書どおりだと遺留分を受け取れない場合、相続人自らが「遺留分を返してほしい」という意思表示をしないと、遺留分を取り返せません。この「遺留分を返してほしい」という意思表示が、「遺留分侵害額請求」と呼ばれるものです。
遺留分のある相続人も、自動的に遺留分を確保できるわけではなく、遺留分侵害額請求を行って初めて遺留分を受け取れます。相続人が定められた期間内に遺留分侵害額請求をしなかった場合には、遺言書どおりの相続が確定します。
(2)遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分の侵害の事実を知ったときから1年以内に行わなければなりません。たとえ相続開始等を知らなかった場合でも、相続開始から10年を経過すれば請求ができなくなります。
(3)遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産、すなわち遺留分を計算するときに基準とする財産は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産のみではありません。被相続人が生前贈与した財産も含まれます。
具体的には、次の計算式のようになります。
遺留分算定の基礎財産=相続財産の価額+生前贈与財産の価額-相続債務の全額
生前贈与財産に関しては、次のものが遺留分算定の基礎財産に含まれます。
- 1)相続人以外の第三者に対し、相続開始前1年間にされた贈与
- 2)相続人に対し、相続開始前10年間にされた特別受益に該当する贈与
- 3) 遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与
(4)遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求の違い
遺留分侵害額請求は近年の相続法改正により定められたもので、令和元年7月1日以降に発生した相続に適用される手続きです。令和元年6月30日以前の相続に関しては、旧法にもとづき、「遺留分減殺請求」を行うことになります。
旧法の遺留分減殺請求では、現物返還が原則でした。たとえば、特定の人に不動産を譲る旨の遺言書により遺留分が侵害されている場合、相続人はその不動産について、侵害されている遺留分に相当する持分を請求できるのみになります。これに対し、新法の遺留分侵害額請求では、遺留分を金銭で評価し、現物ではなく金銭の支払いを請求します。
なお、旧法では「相続人に対する特別受益に該当する贈与」は時期に関係なく遺留分の対象財産に含まれていましたが、新法では10年以内のものに限られる点も変更になっています。
| 相続開始時期 | 令和元年6月30日以前 | 令和元年7月1日以降 |
|---|---|---|
| 遺留分の取り戻し手続き | 遺留分減殺請求 | 遺留分侵害額請求 |
| 請求方法 | 現物返還請求 | 金銭の支払い請求 |
3.遺留分侵害額請求をする方法
遺言書が残されていたせいで、他人が自分の遺留分を相続してしまいそうな場合、どのような手順で遺留分侵害額請求を行えばよいのかを知っておきましょう。
(1)相続人・相続財産調査
自己の遺留分がどれだけあるのかを確認するために、戸籍謄本を集めて相続人を確定する必要があります。さらに、相続財産も調査して、遺留分侵害額がどれくらいなのかも計算します。
(2)内容証明郵便で通知
自遺留分を侵害している相手方に、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。意思表示の方法は決まっていませんが、口頭で伝えても証拠が残らないので、文書で通知します。後日裁判所で争うことになった場合に備えて、内容証明郵便により通知するのがおすすめです。
(3)相手方と協議または調停
相手方と話し合いをし、支払い金額や支払い方法について合意を目指します。話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立て、裁判所で解決する方法があります。
4.遺留分侵害額請求されたらどうする?
遺言書により財産を相続することになった場合、相続人から遺留分侵害額請求をされることがあります。遺留分侵害額請求をされた場合の対処法も知っておきましょう。
(1)遺留分侵害額請求が正当かどうか確認
自分が遺留分侵害額請求をされた場合、まずその請求に根拠があるのかを確認する必要があります。相続財産の中に不動産などが含まれる場合には、評価方法によって遺留分の金額も変わります。遺留分侵害額請求には1年の時効もありますので、時効になっていればそもそもお金を払う必要はありません。
本当に相続人にお金を払わなければならないのか、払うにしてもいくら払わなければならないのかについては、自己判断ではなく弁護士、司法書士等の専門家に確認するのがおすすめです。
(2)金銭がすぐに用意できない場合には?
遺言書で不動産などの現物をもらった場合、遺留分を金銭で返さなければならないけれど、手持ちの現金がないということがあります。この場合には、裁判所に支払いの猶予を申し立てることも可能になっています。
5.まとめ
相続の際、遺言書があれば遺言書の内容どおりに財産分けが行われます。ただし、遺留分のある相続人には最低限の取り分が確保されているため、必ずしも遺言書の内容どおりになるわけではありません。
相続人が遺言書によって奪われた遺留分を相続するためには、遺留分侵害額請求が必要になります。遺留分侵害額請求には1年という時効がありますので、手続きをとるなら早いうちに行わなければならないことも知っておきましょう。

